和解学週間(毎年2月末)
安全保障と人権班のレポート
安全保障と人権班は、2025年2月27日(木)に早稲田大学でシンポジウム「米国の人権外交と東アジア」を行い、対面15名、オンライン40名が参加した。このシンポジウムの目的は、1970〜1980年代における米国の外交政策が東アジア(韓国、台湾、沖縄)の民主化に及ぼした影響を考察することであった。
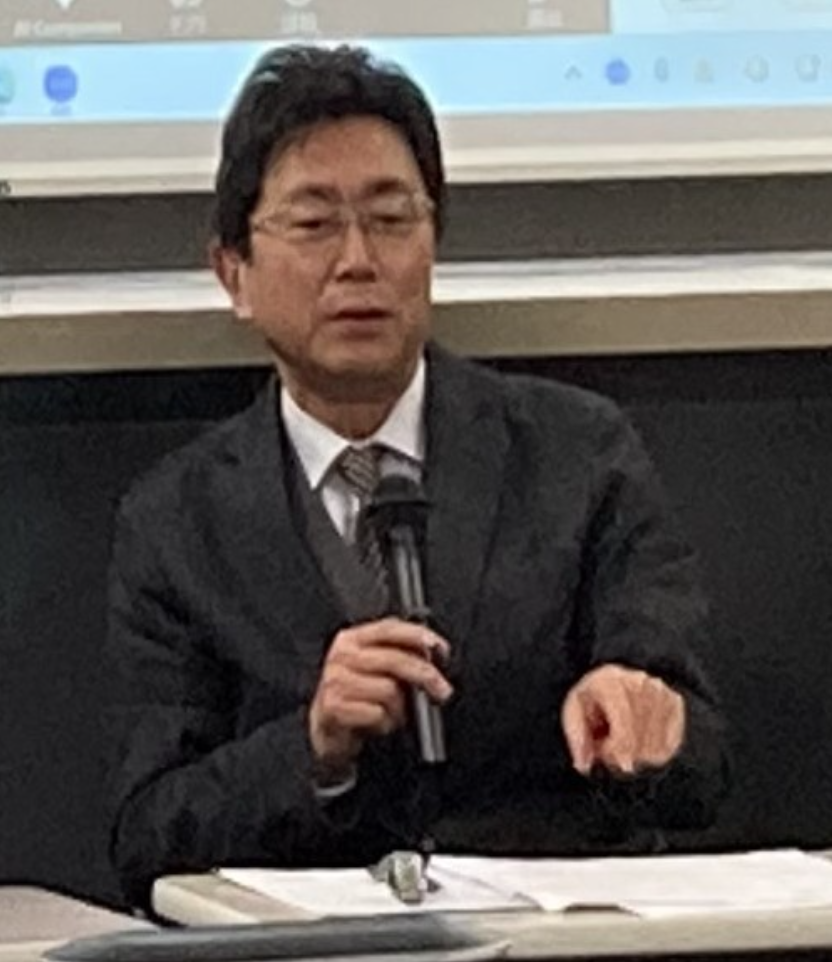
佐々木卓也教授
第一部では、佐々木卓也教授(立教大学)が米国のカーターとレーガン元大統領の人権外交について講演した。南部の人種差別を経験してきたカーターは道徳を重視する外交を行い、エチオピア、フィリピン、イラン、ラテンアメリカの軍事政権に対する軍事援助を削減した。当時は「同盟国に制裁するな」あるいは「制裁が足りない」と批判された。一方で、南アフリカ共和国はカーターがアパルトヘイト廃止運動に協力したことを評価した。2024年にカーターが亡くなると、国内外から惜しまれた。次期のレーガンも人権を擁護する外交を行い、ジェノサイド条約批准に賛成した。
第二部では、若手研究者が米国の人権外交が東アジアの民主化に及ぼした影響について発表した。高賢来講師(関東学院大学)は、カーター外交が韓国に及ぼした影響を述べた。1980年の光州事件では、韓国の軍事政権が市民を弾圧し、カーターは厳しく批判しなかったが、民主化を求めた。平井新講師(東海大学)は台湾が民主化した要因について、アメリカの上院議員が「台湾民主化促進委員会」を設立したこと、また在米台湾人コミュニティがロビー活動を行ったことを説明した。井上史助教(早稲田大学)は、沖縄には日本の官僚や米軍がトップに据えられ、市民主体の民主化は行われなかったと結論付けた。一方で、市民運動の歴史自体は紹介された。
討論者の田中聡講師(立命館大学)はこれらの発表に対して、なぜ米国が他国の人権問題に介入するのか、人権規範はどれほど受け入れられたのかという論点を示した。司会の浅野豊美教授(早稲田大学)は、集合的記憶と人権がどのように関連するのかを各報告者に質問した。東アジアに人権規範が広がり民主化が行われたことが、過去の戦争で戦った国々の和解につながるのではないかという議論が行われた。
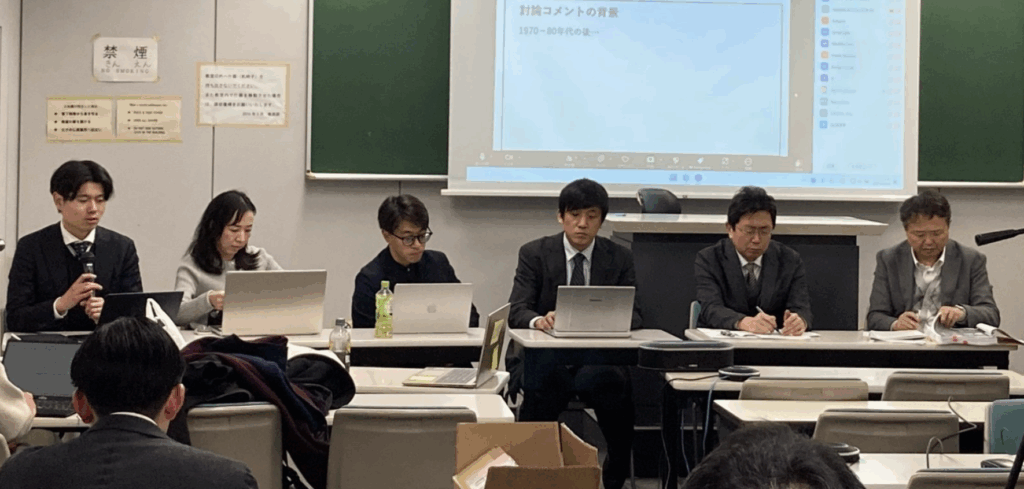
佐々木教授とパネル参加者たち


