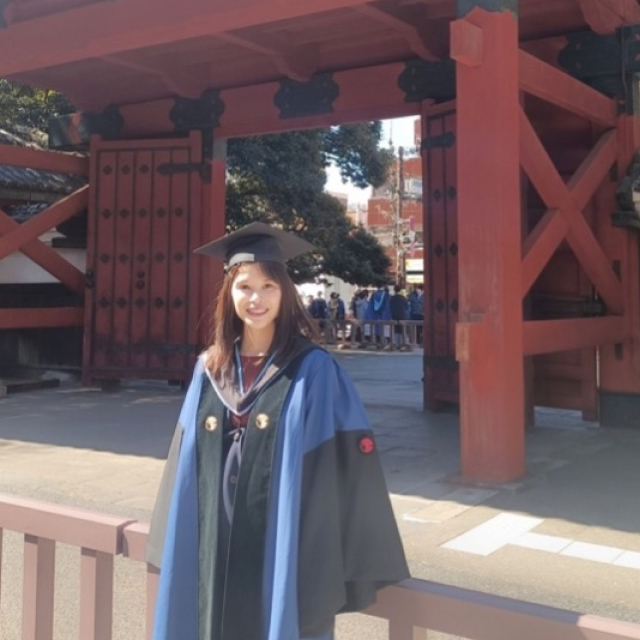早稲田大学和解学フォーラム
【開催報告】2025年6月14日「紛争遺産の解釈をめぐる言説の衝突:平和構築と和解のための対話を育む多様なコミュニティの役割」

(終了後の全員写真)
2025年6月14日、早稲田大学ならびにオンラインのハイブリット形式にて「紛争遺産の解釈をめぐる言説の衝突:平和構築と和解のための対話を育む多様なコミュニティの役割」と題した国際セミナーが開催された。本催しは、早稲田大学(現代政治経済研究所・国際和解学研究所)、ソウル大学校(国際学研究所)、ICOMOS-ICIP、Our World Heritage(OWH)による共催で開かれ、本取り組みは2022年の開始以来4回目を迎えた。プログラムは三部構成であった。会議のビデオクリップは、このリンクから閲覧が可能である。
第一部では「日本の世界遺産の解釈──なぜ不協和が生まれ、いかに和解しうるのか」というテーマのもと、主に新潟県の佐渡金山について議論された。国際関係学の視座から見る紛争遺産や、現地から見た世界遺産登録ならびに展示におけるプロセス、多面的な価値を強調する市民活動の視点など、本事例に関して多角的な報告がなされた。その後の議論では、当事国からの参加者らが歴史教育について言及する場面もあった。歴史共同研究の提言がされたことに対して、過去既にある二度の失敗に関する指摘がされ、だからこそ「国際和解学」の意義があるという主張も見られた。日本と韓国出身の参加者が中心的に議論する一方、「第三者的意見」ともいう、他国から見た視点も非常に有益であった。
ランチ休憩を挟んだのち、第二部はアジア圏のみならず、世界の幅広い事例を扱ったセッションとなった。アジアからは台湾が紹介され、ほかの地域では欧州、中東ならびにアフリカのケースが報告された。「紛争遺産」という同一テーマのもと、多岐にわたる問題群が存在することを象徴する多様性であったのと同時に、各々特有の文脈を超えた問題の普遍性を示唆する内容でもあった。
最後の第三部では、100名近くの応募から選ばれた5名の若手研究者による報告が行われた。発表後、報告をした若手研究者全員に対して、討論者から幾つかのコメントがあった。各参加者の内容に対して、それぞれ丁寧に指摘を行うものもあれば、総じて若手研究者に問いかけることもあった。そのひとつは、ある種政治的な概念でもある「和解」と自分の研究が接していることを指摘した上で、自分の研究が思わぬ形で活用されないために、改めて研究内容そのものについて再考をすることであった。若手研究者にとって、今後の研究路線を考える上で大変貴重な時間となった。また、会場の受付前では同時に、ほか若手研究者によるポスターセッションも実施された。
本国際セミナーの慣例として、その会をひと単語で表すことがある。今回取り仕切りを務めたDr. Jihon Kimは、今年の単語に「Joint」を選んだ。昨年の単語である「Action」と合わせて「Joint Action」になることも踏まえ、来年以降の引き続きの開催が目論まれる。なお、浅野豊美教授による開会挨拶はこちらの記事を参照されたい。